吉村昭をつづけて読んでいる。
今回は『漂流』。(新潮文庫)
時は、1785年(天明5年)。
土佐の船乗り・長平は、シケに遭い、黒潮に乗ってしまう。
やがて絶海の火山島(青ヶ島のはるか南にある鳥島)に漂着。
そこは、水も湧かず、食べものもない無人島だった。
仲間の男たちが次々と倒れていくなか、
アホウドリ(渡り鳥)の肉と雨水、わずかな魚介と海草で
12年間なんとか生き続け、ついに生還する───。
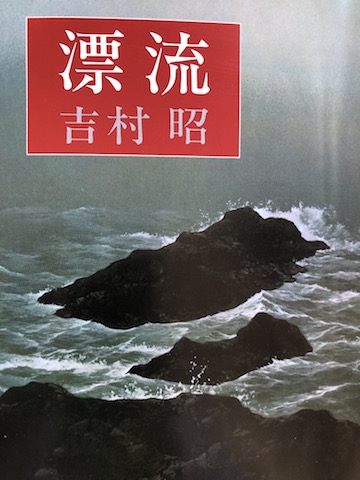
吉村昭は、限界状況のなかで格闘する人間を好んで描く。
限界状況になると、否応なく、その人間のリアルな「骨」が露出する。
まさに実存状態になるからだ。
地獄の底に落ちていくような時化や漂流のシーン、
仲間がひとり、またひとり死んでいく光景もリアルで恐ろしいが、
島から脱出しようと、
アホウドリ(翼を広げると2.4mほどもある)を背負って飛び立とうとしたり、
渡りをするアホウドリの首に木札をつけ、
その手紙を運んでもらおうという場面などは、
あまりにかなしく、自然と向き合ったときの、人間存在の小ささに乾いた笑いがわく。

鳥島(海上保安庁撮影)
吉村昭の小説はディテールがすごい。
綿密な取材による、しっかりとした「骨組み」。
そのうえに、無駄のない肉がついている。
歌い上げるのではなく、事実を事実として描くことで、
ハードでソリッドな叙情が立ち上がってくる。
*
作家・高井有一による、文庫の解説がまた素晴らしい。
吉村昭の文章の魅力をこう書く。
●独りよがりの幻想に溺れたりはしない。
●意味ありげな言葉を連ねたりはしない。
●正確で節度のある視線

上空から見た鳥島(海上保安庁撮影)
『漂流』の主人公・長平は、
とにかく「希望」を意識して生きつづけようと思う。
が、限界状況のなか、自殺を考えることもあった。
長い年月、たましいの揺れを経ることで、
じょじょに無駄なあがきをやめるようになる。
運命という波に、身をゆだねることを知っていく。
まさに「他力」というものを体得していくのだ。
このあたりが、読んでいて、とても納得できるし、
いまのひどい時代を生きるうえで、参考になる。

ヴィクトール・フランクル『夜と霧』
「希望をもつ」こと。
これは、ナチスの収容所で暮らした精神科医ヴィクトール・フランクルの著書
『夜と霧』でも言及されていることだ。
こちらはこちらで、この世の地獄からの生還者だが、
いまのこのひどい時代、
ぼくらが落ちこんだり、ひねくれたり、無駄に怒ったりせず、
まっとうに正気で生きていくうえで、
いちばん大切なことではないか。
ひるまず、弱気にならず、斜にかまえず、
光はあまねく万民に射していることを忘れず、
まっすぐに生きていこう。
そう思った。

